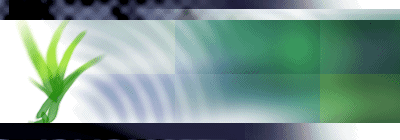2013年1月6日-筆写
The Sound of Running Water
これまで私が何かの友情をつちかったことがあるかどうか、私は覚えていない。けれども私の友人になりたがったものは大勢いた。たくさんの人々が私と友達になった。そして彼らは私の友となることを楽しんだ。というのも、私を敵にまわすことは不可能だったからだ。だが、私の方から友達になるために誰かのもとを訪ねたという記憶はない。私が決して友情を歓迎しなかったというのではない。もし誰かが私の友人になれば、私は真底からそれを迎え入れた。だがそのときですら、私はふつうの意味の友達にはなれなかった。私はいつも超然としたままでいたからだ。
つまり、学校で学んでいたあいだでさえ私は超然としていた。私は、教師の誰とであろうが、学生仲間の誰とであろうが、他の誰とであろうが、私を没頭させるような、孤島としての私の存在を壊すような友情を進展させることができなかった。友達が来て私の家に泊まりもした。私は大勢の人々にも会った----。私は友達をたくさん持っていた。だが私の側にはそのために彼らを頼ったり、彼らを思い出したりするようなものは何もなかった。
私が誰も思い出さないことに注目するのは実に興味深い。今彼が会いにきてくれれば非常に嬉しいのにと感じながら、坐って誰かのことを思うことなど一度も起こらなかった。もし誰かが私に会ってくれればとても嬉しい。だが、誰かに会えないからといって不幸になることはない。究極の歓喜の状態に対してその責を負うのは私の祖父の死のみであると私は信じる。その死によって、私は永久に私自身に投げ返された。私はその中心から逆戻りできないでいる。アウトサイダー、異邦人であるこの状態のおかげで私は新しい体験の次元を見た。
私は自分自身にとっての宇宙になった。この新しい体験、それにしても不思議な体験は、喜ばしい痛みではあったが、私にある種の痛みを与えた。それはこのようなものだった。つまり、私はその若さで、ある種の成熟と年長者たることを感じ、体験し始めたのだ。
この体験のなかにはエゴは巻き込まれていなかった。だが個体性は依然そこにあったので、そのため私はいくつかの当惑すべき状態に置かれた。
例えば、私にはいつでも学生になる用意ができていたのにもかかわらず、誰ひとり私の教師として受け容れることができなかった。私は自分の師(マスター)と呼べる人をひとりも見い出さなかった。私が見い出したのは、非常に生に巻き込まれていて、生と共にある人ばかりだった。死を見たことのない者は決して私の教師にはななかった。私は尊敬したかったが、それは無理だった。私は河や山、そして石さえも敬うことができたのに、人間は駄目だった。それはきわめて当惑すべき状況だった。そしてそのために私は非常に困難な境遇のもとに置かれた。
私は自然に敬うことができるような教師に出会わなかった。というのも、それなくしては生が意味を持てないような絶対の真実があって、それを知っている者がいるという感触を一度も得たことがなかったからだ。何度も私は、当時の私でさえ言ったりしたりしないような子供じみたことを、いろいろな教師が言ったりしたりしているのを感じていた。そのため、私は一度たりとも自分が小さな子供であり、誰かの保護と指導のもとにとどまるべきだとは感じなかった。私が誰のもとにも行かなかったというのではない。私は大勢の人を訪ねた。しかし私はいつも、伝えられたことは自分でも知っていると思いながら得るものもなく帰ってきた。彼らから学べるものは何もなかった。
そのため、面倒なことが生じた。何度も他人は私のことをエゴイストだと見なした。彼らがそう感じたのも無理はない。なぜなら、私は誰を尊敬することも、敬意を払うこともできず、誰の命令に従うこともできなかったからだ。誰もが私を無遠慮で扇動的な反逆者だと感じた。ある年齢に達するまで、私の教師や年長者や全ての人にとって、私は無作法で反逆的で扇動的でエゴイスティックな人物として通っていた。そして彼らは、私が生涯誰のどんな役にも立つまいとあきらめていた。
彼らが素朴に信じていたどんなものも、私はまったく信じることができなかった。そして彼らが決して疑わなかったことを私はいつも疑った。彼らがいつも前に立って合掌礼拝する何に対しても私は手を合わせることさえできなかった。私はそうする気持ちに一度もならなかった。私は自分自身を欺こうとしたことは一度もないし、どんな偽善も身につけなかった。私に信頼がなければ、ないのだ----、私にはどうしようもない。私は自分が真実だと信じていないことは何ひとつ見せつけようとはしなかった。
そのためにいくつかの困難が生じたが、利点もあった。私は別の方向からも自分自身に投げ返された。なぜなら、私は一度たりとも真実が他者から学べるとは信じたこともなければ感じたこともなかったからだ。学ぶための道はただひとつ。自分自身から学ぶしかなかった。そのため私は、私の導師(グル)たり得る人をひとりも知らなかった。私が私自身の導師(グル)であり、私自身の弟子でもあった。私が盲目的に誰かに従うことができないとしたら、残された唯一の道は自分なりのやり方で探究することだった。誰も私の従うべき道を指し示してくれる人はいなかった。私は独りで歩かねばならなかった。
〜神秘の次元 5章〜
TOP 1939年〜1946年 アウトサイダー
ラジニーシは自分の新しい環境への探検を中断することには何の関心もなかったので、9歳になるまで学校に行かなかった。しかしそのときがくると、すぐさま彼の風変わりな、ひとりで満たされている雰囲気は、磁石のように他の多くの者たちを惹きつけた。そしてすぐに、彼はあらゆる年代の手に負えない悪童グループのリーダーに自然になっていた。彼らの大半は何年ものあいだ切っても切れぬ仲となり、どの少年グループでも試みるようなとびきりの、とてつもない実験をいくつか楽しんだ。
子供の頃、私はある師、水泳師範のもとに送られた。彼は町一番の泳ぎ手だった。私はあんなにも深く水を愛している人を見たことがない。彼にとって水は神だった---。彼は水を礼拝した。そして河は彼の家だった。早朝3時、彼はもう河にいる。夕方、彼は河にいる。夜、彼は河のほとりに坐って瞑想している。彼の全人生が河の近くにいることで成っていた。
彼のもとに連れてゆかれると---私は泳ぎ方を習いたかったのだ---彼は私を見て何かを感じた。彼は言った。「でも泳ぎ方を習う方法なんてないんだよ。私にできるのは君を水のなかに放り込むことだけだ。そうすれば泳ぎはひとりでにやってくる。それを習う方法なんてない---、それは教えられることではない。それは知識ではなくてこつなんだ」
そして彼はそのとおりにした。彼は私を水のなかに放り込んで岸辺に立った。私は二度三度と沈み、今にも溺れるかと思った。彼はただそこに立っていた。彼は私を助けようともしなかった! 当然、生命が危ないとなると、人はできることなら何でもやる。そこで私はもがき始めた。でたらめに、無我夢中で手を振りまわしたが、こつがつかめた。生命が危なくなると、人はできることなら何でもやる。そしてできることを何でも全面的にやれれば、必ずものごとが起こる!
私は泳げた! 私はわくわくした! 私は言った。「今度は僕を放り込まなくてもいいよ、自分で飛び込むから。もう身体が自然に浮くことがわかったんだ。これは泳ぐという問題じゃない----、水の力と調子を合わせるというだけの問題なんだ。一度水の力と調子が合えば、水が守ってくれるんだ」
子供の頃、私は朝早くよく河に行った。それは小さな村で、河はまるで少しも流れていないかのように実にゆったりとしていた。朝、太陽が昇る前など、あまりにゆったりと静かなので河が流れているかどうかわからないほどだった。朝、人影もなく、沐浴する人たちもまだきていないとき、河は静まりかえっている。小鳥たちさえさえずらない早い朝---。音もなく、静寂だけがみなぎり、そしてマンゴー樹の香りが河全体にたちこめている。
私はよくそこに行った。河の最も遠い曲がり角にゆき、ただ坐り、ただそこにいた。何もしなくてよかった。ただそこにいるだけで十分だった。そこにいることが非常に美しい体験だった。私は水浴びをし、泳ぎ、陽が昇ると向こう岸の広大な砂地に行き、太陽のもとで身体を乾かしたものだ。そこに横たわり、ときには眠りこむことさえあった。家に戻ると、母はこう尋ねたものだ、「朝のあいだずっと何をしていたの?」私は「何も」と答えたものだ。なぜなら、実際私は何をしていたわけでもないからだ。すると彼女はこう言った。「そんなはずないでしょう。何時間もここにいなかったのよ。何もしていなかったはずがないわ。きっと何かをしていたにちがいないわ」そして彼女は正しかった、だが私も間違ってはいなかった。
私はまったく何もしていなかった。私は何もせずものごとが起こるにまかせて、ただ河と一緒にそこにいただけだ。泳ぎたくなったら・・・・、覚えておきなさい、泳ぎたくなったらだ、そうなったら私は泳いだ、だがそれは私の側ですることではなかった。私は何も押し付けていなかった。眠くなったら、私は眠った。ものごとは起こっていたが、行為する人はいなかった。そして私の最初の光明の体験はその河の近くで始まった。何もしないでただそこにいるだけで、数多くの出来事が起こった。
だが母は、私が何かしていたにちがいないと言い張った。そこで私は「わかったよ、水浴びをして、太陽で身体を乾かしていたんだよ」と言った。すると彼女は満足した。でも私は満足しなかった。なぜなら、そこで、河のなかで起こったことは、「水浴びをした」という言葉で表現されるようなことではなかったからだ。それではあまりに貧相で血が通っていない。河で遊び、河に浮かび、河で泳ぐことはあまりにも深い体験だったので、ただ「水浴びをした」と言うだけでは何の意味もなさなかった。あるいは「あそこに行って、土手を散歩して、坐ったんだ」と言うだけでは何も伝わらない。
〜 Tantra: The Supreme Understanding 存在の詩 〜
1939年〜1946年 第二の7年間 ----河
若きアウトサイダーは今やガダルワラのにぎやかな市場町に住む両親のもとに戻った。彼が幼年期の残りと思春期を過すことになった家は、理想的にも近くに地方のジャイナ教寺院があるシャッカー河のほとりに位置していた。その広い河は、気持ちよく澄んだ水と河岸を取り巻く美しくてめずらしい小石によって深く愛されていた。それは少年の新しい生活のなかで、ひとつの中心的な焦点になるべきものであった。