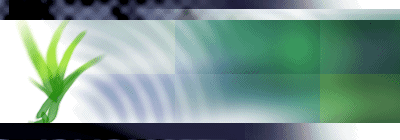2013年1月8日-筆写
The Sound of Running Water
3つのグナの実験 ---- それを行なう最も科学的な方法
それぞれのブッダフッド(覚者の性質)にはある優位を占める特質がある。この新しいブッダは、エクスタシーに満ちた探求の本性と、止むことなく自分自身に働きかけ実験をし続けてゆく詩人=科学者の本性を持っていると言ってもいい。彼の注意は今や3つの大いなる生命力、エネルギーの3大特質、あるいは3大原理----、タマス、ラジャス、サットヴァに向かうことになる。
光明を得た存在はそれぞれこうした原理のひとつ、あるいはそれ以上を表現する。老子やラマナ・マハリシの両者に顕著な特質はタマス、即ち不活動、不活発の原理であると言われる。キリストやマホメッドは活発で火のようなラジャス・グナの表現を用いる。仏陀の中ではサットヴァの原理が支配的であり、クリシュナの中では同時に3つすべてが働いている。
さらにもうひとつの可能性がある。私は自分自身の実験のなかでそれを使ってきた。3つの特質すべてを私は使った。同時にではなく、順を追って。私の見解によると、それこそそれを行なう最も科学的な方法だ。
我々は3回の7年周期の後、プーナに移転する1974年までの21年間の後を追う。このパターンは意義深いものではあるが、こうした区分を重要視しすぎてはならない。それは行為のなかにある複雑な未知の力の有用な指標として与えられている。光明に続く歳月は、素早く過ぎ去る事件に取り巻かれた3つの原理として描くことができる。
実際、その原理のひとつは、すでに7年間というもの舞台に登場していたようだ。それはタマスの原理だ。そしてこれは、次の7年間を通じて50年代の終わり頃にラジャスの原理がそのあとを引き継ぐまでずっと続くことになった。そのラジャスは次の14年間、穏やかなサットヴァの原理がプーナ時代初期にその火を消すまでずっと燃え続けた。
ラジニーシはとにかく少し気違いじみていると認められていたので、彼の存在の外面的な変容は仲間たちに気づかれずに過ぎていった。当時彼の面倒を見、その変化の前後まじかに彼を見ていた従兄弟ですらこれといって変わった点を彼の日常に見い出すことはなかった。そうして彼は大学生活を通じて見るからに奇妙なふるまいを続けた。
最初の数年は老子のようにタマス・グナの神秘の実験に費やされた。私の老子に対する愛着はそれゆえ根本的なものだ。私は何事に関しても怠惰だった。無為こそ私が求めていたものだった。私は避けられないことや強制されたことを除けば可能な限り何もしなかった。私は理由がなければ手や足を動かすことさえしなかった。大学の最終学年のとき、ひとりの哲学教授がいた。たいていの哲学教授がそうであるように、彼も頑固で変わり者だった。彼は女性は決して見ないと固く心に決めていた。不運なことに彼のクラスには二人の学生しかいなかった。一人は私でもう一人は女の子だった。そこでその教授はずっと目を閉じたまま教えなければならなかった。
私にとってそれはもっけの幸いだった。彼の講義中私は居眠りしていたからだ。教室に女の子がいるので、彼は目を開けるわけにはいかなかった。ところが、教授は私にとても満足していた。というのも彼は私も女性を見ないという主義を信じているものと思い込んでいたからだ。学内に少なくとももうひとり女性を見ない者がいるというわけだ。そのためふたりきりで出会うと彼は何度も私に、「君こそ私を理解できる唯一の人だ」と言った。
だがある日私のこのイメージは消された。教授にはもうひとつ別の癖があった。彼は自分の授業時間が一時間とは信じていなかったので、大学はいつも彼に最後の時間を与えていた。彼は、「講義をいつ始めるかは私の手の内にあるが、それを終わらせることは私の手の内にはない」と言っていた。だから彼の講義は60分になるかもしれないし、あるいは80分、90分になるかもしれなかった。そんなことは彼にとっては何の違いもなかった。彼はいつも、授業の終わりを知らせるベルが鳴っても必ず話を止めるとは限らないと言っていた。きり出した主題が完結して初めて話すのを止めるのだった。そこでその80分、90分のあいだ、私は彼のクラスでよく眠ったものだ。
その子と私の間には、授業が終わりに近づいたら彼女が私を起こしてくれるという暗黙の諒解があった。ところがある日、彼女が授業の途中で誰かに急用で呼ばれて行ってしまった。私は眠り続け、教授は講義を続けていた。授業が終わると彼は眼を開けて、私が眠っているのを見つけた。
彼は私を起こすとどうして眠っていたのかと尋ねた。私は彼にこう言った。「やっと僕が眠っているのを見つけましたね。いいですか、僕は毎日眠っていたのですよ。僕は若い女性に苦情など持っていませんし、あなたの講義の最中に居眠りするのはとても気持ちがいいんです」
ジャバプール大学在学中
もうひとり私の教授がいたが、彼も私のよき友人だった。彼も私同様怠惰だった。彼も私と同じ独り暮らしだったので、相部屋にした方がいいと持ちかけてきた。私は彼に、そうすると何か面倒なことが起こるかもしれないと言った。思うにまず間違いなく、私が彼の眠りの邪魔をするか彼が私の眠りの邪魔をするだろう。
しかし彼がそれでも一緒に住むことを望むなら、いくつかの取り決めをかわす必要があった。なぜなら、私たちはどちらとも怠け者だったからだ。今でも彼は当時と変わらない。彼は彼のこの性質を捨てていない。だが彼はこの性質を瞑想のなかの実験にしたことが一度もない。さもなければ、彼は今頃それを超越していることだろう。
この友人の教授と私が一緒に暮らし始めた最初の日、私はふたりの取り決めをどういうものにするか決めねばならなかった。それまで私たちは別々に暮らしていたので、特別な取り決めをかわす必要はなかった。結局彼が、早く起きた方がミルクを持ってくることにしようと提案した。私はすぐに同意した。私は喜んだし、彼も喜んだ。だがふたりとも幻想を持っていたのだ。私は朝、先に起きなくても済むと思っていたのだが、驚いたことに彼も同じことを考えていた。
次の朝、9時頃に私は目を覚ました。見ると彼が眠っているので、私はまたひと寝入りした。彼は朝10時に目を覚まし、私が眠っているのを見た。彼も眠ろうとしたのだが、彼の場合は問題があった。つまり彼は11時に大学に行かねばならなかった。何と言っても彼にとっては勤めであり、私は学生に過ぎなかった。従って私には行く必要も強制もなかった。実際、私は一度も規則正しく大学に出席したことがなかった。
最後にはいよいよ必要性に迫られて、彼が起きてミルクを取りに行かねばならなかった。彼が戻ってくる頃には私も起きて座っていたものだ。彼は私に、こんなことが毎日の問題になるようではこういうタイプの友情はうまくゆかないと言った。彼が言うには、自分は大学に行かねばならないからせいぜい10時までしか寝ていられないが、私の方は一日中でも待っていられる。それでは自分が毎日ミルクを取りに行かねばならないことになり、そんな具合では、友情が続くはずがないと言うのだった。
私は何であれ何かするのを控えることを自分の第一原理にした。大学の寄宿舎にいたその2年間、私はドアから部屋の外に一気に飛び出せるように寝台を部屋のちょうど入口に据えた。「わざわざ部屋中を横切る必要がどうしてある?」と私は感じた。私は部屋の中に入りたいとも思わなかったし、部屋を掃除することなど論外だった。しかしそれにはある種の喜びがあった。
〜神秘の次元 6章〜