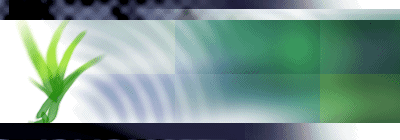The Sound of Running Water
果てしない落下---足を置く地面や場所はどこにもなかった
次の3年間、青年はますます常軌を逸し、矛盾に満ちるようになった。それは彼がますます自分につきまとい始めた奇妙で神秘的な現象に対処しなければならなかったためだ。彼には導く師(マスター)もなく、ひとりだった。
私はヴァイディヤ、医者の元にも連れて行かれた。実際、私はいろいろな医師、いろいろな医者のところに連れて行かれた。たったひとり私の父に、「彼は病気ではありません。時を無駄にしてはいけません」と言ったアユールヴェーダのヴァイディヤがいた。むろん家族の者たちは私を方々に引っ張りまわした。たくさんの人が私に薬をくれた。私は父に言ったものだ。「どうして心配するの? 僕はほんとに大丈夫だよ」だが誰も私の言葉を信じなかった。彼らは「お前は安静にしていなさい。ただ薬を飲んだって悪くはないだろう?」と言うのだった。そこで私はあらゆる種類の薬を飲んだものだ。
たったひとりだけ洞察力を備えたヴァイディヤがいた。彼の名はパンディット・バギラット・プラサードといった。彼の娘はプーナに住んでいる。彼女は医者と結婚した。その老人は死んでしまったが、洞察力のある稀な人物だった。彼は私を見て「彼は病気ではありません」と言うと、泣き出してこう言った。「私は自分でもこのような状態を探求してきたのです。彼は幸運だ。私は今生では取り逃してしまった。彼を誰のもとにも連れて行ってはなりません。彼はわが家に帰り着こうとしているのです」そして彼は喜びの涙を流して泣いた。
彼は探求者だった。彼は国中をくまなく探した。彼の生涯は探求と問いかけだった。彼はそれについて何がしかの知識を持っていた。彼は私の保護者になり、医者や他の医師のたちから私を守ってくれた。そして彼は父に、「任せておきなさい。彼の面倒は私が見ましょう」と言った。彼は決して私に薬を渡さなかった。父が要求すると砂糖の錠剤を私に渡してこう言った。「これは砂糖の錠剤だ。彼らを安心させるために飲むのもいいだろう。害もなければ助けにもならない。実際、どんな助けも可能ではないのだから」
Tao: The Pathless Path : vol.2 9章
TOP 第二のサトリ
状態が悪化するにつれて、見た目にも彼の様子があまりにも奇妙で不可解なものになったので、家族の者たちは慌て始めた。ラジニーシは薬は役に立たないと言い張ったが、彼らは依然21歳で彼が死ぬという占星術師の予言が的中するかもしれないと思い、彼を次から次へと医者に連れて行った。
一年のあいだずっと、私には自分を生かしておくことすら困難だった。ただ自分を生かしておくことだけでも非常にむずかしいことだった。なぜなら食欲がすっかり消え失せてしまったからだ。日々は過ぎてゆくのに、私は少しも空腹を覚えなかった。日々は過ぎてゆくのに、私は少しも渇きを覚えなかった。
私は無理やり食べ、無理やり飲まねばならなかった。肉体の実在感があまりにも稀薄だったので、自分がまだ肉体のなかにいることを感じるために我とわが身を傷つけねばならなかった。自分の頭がまだそこにあるかどうかを確かめるために、頭を壁にぶつけなければならなかった。痛みを感じるときだけ私は多少肉体のなかにいた。
毎朝毎夕、私は5マイル(8km)から8マイル(13km)走った。人々は私が狂ったと考えた。そんなに走っていたのはなぜか? 一日に16マイル(26km)も! ただ自分を感じるためだった。自分がまだいることを感じるためだった。自分自身との接触を失わないためだ---起こりつつあった新しい出来事に私の眼が慣れるのをただ待つためだった。
それに、私は自分を自分自身に引きつけておかねばならなかった。私は誰とも話しをしようとは思わなかった。なぜなら何もかもがあまりにも脈絡を欠いてきたので、ひとつの文章を明確に述べることすら困難だったからだ。文章の途中で私は自分が何を言おうとしていたのかを忘れた。道の真ん中で自分がどこへ行こうとしていたのかを忘れた。だから戻らなければならないほどだった。本を読めば、50ページほど読み進んで突然思い出した。「何を読んでいたのだろう? まったく思い出せない」私の状態はそんな有り様だった。
ひとつの文章を完結させることさえ困難だった。私は自分の部屋にこもらなければならなかった。私は何も言わないことに、何も話さないことにした。何を話しても、自分は気違いだと言っているようなものだからだ。一年間それは続いた。私はただ床に横たわり、天井を見つめ、一から百まで数え、また逆に百から一まで数えた。数を数えることができているというだけでやっとだった。何度も何度も私は忘れた。焦点を取り戻し、遠近感を得るには一年かかった。
それは起こった---それは奇蹟だった---だがそれは困難だった。私に力を貸してくれる人はひとりもいなかった。私がどこに向かっているのか、何が起こっているのかを言ってくれる人はひとりもいなかった。実際、すべての人がそれに反対した。私の教師や友達、好意を持つ人々---、みんながそれに反対した。だが彼らは何もできなかった。彼らにできたことといえば、ただ私を非難し、いったい何をしているのかと尋ねることだけだった。
私は何もしていなかった! 今やそれは私を超えていた。それは起こっていた。私は何かをやってしまった。そうとは知らずに私は扉を叩いてしまった。今や扉は開いた。私は何年もただ何もせず静かに坐って瞑想してきた。そしてやがてそのスペースに、そのハートのスペースに入り始めた。そこではあなたはいる、だが、あなたは何もしていない。あなたはただそこにいるだけだ。ひとつの現存、目撃者だ。
あなたは目撃者ですらない。なぜならあなたは見守っているわけではないからだ。あなたはまさに現存だ。言葉は適切ではない。というのも、たとえどのような言葉が使用されても、あたかも何かがなされているかのような印象を与えるからだ。いや、私はそれをやっていなかった。私はただ横になり、坐り、歩いていただけだ---。奥深くには行為者がいなかった。私はあらゆる野心を失っていた。誰になろうとする欲望も、どこかに---神にすら、涅槃(ニルヴァーナ)にすら---行き着こうとする欲望もなかった。私はただ自分自身に投げ返された。
Tao: The Pathless Path : vol.2 9章
心と肉体、両方との繋がりを失い始めたので、彼は意識を保ち、正気でいるために、そして命を保つためにすら奇妙でしばしば異様な技法(メソッド)を思いついた。
私の状況はまったくの暗闇だった。あたかも深くて暗い井戸の中に転落したかのようだった。その頃、私は何度も底なしの井戸の中を落下して落下して、深みへ降りてゆく夢を見た。そして何度も汗をびっしょりかき、汗まみれになって夢から醒めた。というのもその落下は果てしがなく、足を置く地面や場所はどこにもなかったからだ。
暗闇と落下の他には何も残らなかった。だが私は除々にその状況さえも受け容れた。誰かに同意するかもしれない、何かにしがみつくかもしれない、何かの答えを受け容れるかもしれないと感じたことは何度もあったが、それは私の本性にそぐわなかった。私はどうしても他人の考えを受け容れることができなかった。
Dimensions Beyond The Known: 「神秘の次元」
2013年1月8日-筆写