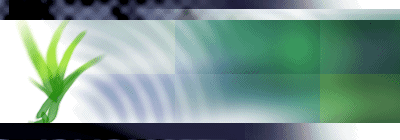2013年1月5日-筆写
The Sound of Running Water
1931年〜1938年 最初の7年間 --- 最初で最後の関係
ラジニーシ・チャンドラ・モハンは、1931年12月11日、インド中部のクチワダという小さな村で生まれた。彼は5人姉妹と6人兄弟の長男だった。彼は、仏陀と同時代に光明を得たティルタンカール・マハヴィーラをその偉大な導師とする厳格で今なお盛んな宗教教団、ジャイナ教の共同体に生まれた。
最初の3日間、子供は泣きもせず少しもミルクを口にしなかったという。それはあたかも7世紀を隔てた21日間の断食を完結しているかのごとくだった。
彼の母方の祖父はよく知られていて敬意を集めている占星術師に相談した。彼は奇妙で不吉な前兆を見つけ出した。
インド、マディヤ・プラデッシュ、クチワダのOshoの生家
現在の生家
占星術師は私のクンダリ、私のバース・チャートを作ろうとした。彼はそれを調べて言った。
「7年経ってこの子が生きていたら、その時初めてチャートを作りましょう。この子が7年以上生きるのは無理のようです。だからクンダリを作ってみても仕方ありません。」
それ以来、家族の者たちはみんな彼の死のことで頭を悩ませた。
私は幼年時代の初期を母方の祖父母の家で過した。そして私は彼らを深く愛していた。私の母は彼らのひとり娘だった。彼らはとても淋しい思いをしていたので私を育てたがった。そこで私は7歳になるまで彼らと共に滞在した。私は彼らを自分の父母とみなしていた。彼らは非常に裕福で、衣食住には何一つ不自由がなかった。私は王子のように育てられた。私は祖父を非常に愛していたし、彼も私を愛してくれて、生きているあいだは一度も私を両親のもとにゆかせてくれなかったほどだ。「私が死ぬまで行ってはいかん」と彼は言った。
彼方なるものの覚醒がどのようにして7世紀前からもちこされ、年若いインドの少年の日常生活に溶け込んでいったかはわからない。だが和尚は、英国の統治が終わろうとする時代を生きた少年なら誰もが送ったような正常で高い精神的生活を送った。依然としてそこはキプリングのインドでもほとんど触れられていない地域であり、学校や近隣の町から30マイル以上も離れた、静かであまり人が訪れることのない村だった。
占星術師の不吉な警告は、ある意味で正しかったことが判明した。
私は7歳になっても生き延びたが、深い死の体験を味わった---。それは私の死ではなく、私の祖父の死だった。そして私は彼に深い愛着を感じていたので、彼の死は私自身の死のようだった。
まさにその死の最初の一瞥が彼を見舞った時、祖父は口がきけなくなった。私たちはその村で24時間彼の様態を見守った。だが、よくなる兆しはなかった。私は、彼が懸命に何かを言おうとしていたのを覚えている。だが彼は話せなかった。彼は何かを言いたかったのだが、それを言うことができなかった。そこで私たちは彼を牛車に乗せて町に連れて行かねばならなかった。ゆっくりと、あいついで、彼の感覚は消えていった。彼はすぐには死なず、じわじわと苦しみに満ちていた。まず口がきけなくなり、それから耳が聞こえなくなった。続いて彼は眼をも閉じた。私は牛車に乗ってそばで一部始終を見守っていた。そして町は32マイルも遠く離れていた。
起こっていることは何もかも当時の私の理解を超えているように思われた。私が死を目撃したのはこれが初めてだった。私は彼が死につつあるということを理解することさえしなかった。だが除々に、彼の感覚はすべて消えてゆき、彼は無意識になった。私たちが町に近づいた頃、彼はすでに半分死んでいた。呼吸はまだ続いていたが、他はすべてなくなっていた。その後彼は意識を回復しなかったが、3日間呼吸を続けた。彼は無意識のなかで死んだ。
彼のこの緩慢な感覚の喪失と最終的な死は、私の記憶に深々と刻み込まれるようになった。私が最も深い関係を持ったのは彼とだった。私にとって、彼は唯一の対象だった。そしておそらく彼の死ゆえに、私は他の誰に対してもそれほど愛着を感じることができなかった。それ以来、私は独りだった。
彼は私の一部になりきっていた。私は彼の現存、彼の愛のもとで大きくなった。彼が死んだ時、私はそれを感じた。今やそれは受けねばならない大きな試練だった。もう私は生きたくなかった。それは幼稚だったが、それを通して何か非常に深いことが起こった。私は3日間、ずっと横になっていた。私はベッドから出ようとしなかった。私は、「彼が死んだのなら、生きてはいたくない」と言った。
孤独の事実が7歳のときからずっと私をとらえた。孤独は私の本性になった。彼の死は私をあらゆる関係から永遠に解き放った。彼の死は、私にとってあらゆる執着の死となった。その後私は、誰とも関係の絆をしっかり結べなかった。誰かとの関係が親密なものになり始めると、必ずあの死が私を見据えた。それゆえ、いくらかの愛着を覚える相手のそばにいると、今日ではないにせよ明日になればあの人も死ぬかもしれないと感じた。
私にとって、愛は必ず死を想起させるようになった。それは、死を意識することなく愛することが私にはできなかったという意味だ。友情はあり得た。慈悲はあり得た。だがどんなものにも我を忘れて夢中になることはあり得なかった。したがって、生の狂気が私に影響を及ぼすことはなかった。生のなかに押し込まれるようになる前に、死が私を見据えた。
私にとって他の誰かが私の「中心」になるという可能性は、まさに人生の第一歩で破壊された。つくられた最初の中心はくずれ落ち、言うなれば、私は私自身の自己に投げ返された。
あとになって私は、感じやすい年頃にこうして死を間近で観察したことは、最終的には、私にとって祝福がその姿を変えたものだったと感じるようになった。このような死がもっとあとで起こっていたら、おそらく私は祖父の身代わりを他に見つけていただろう。もしも私が他者に関心を寄せるようになっていたら、私は自己に向かう旅の機会を失っていただろう。私は他の人たちにとって一種のよそ者になった。総じてこの年代に、私たちは他者と関係するようになる。その頃私たちは社会に組み入れられる。それは私たちが、いわば、私たちを吸収したがっている社会によって得度(イニシエート)される年頃だ。だが、私は決して得度(イニシエート)されなかった。私は個人として入っていった。そして私は孤島のように超然と離れたままだった。
〜神秘の次元 5章〜
TOP 1939年〜1946年 第二の7年間